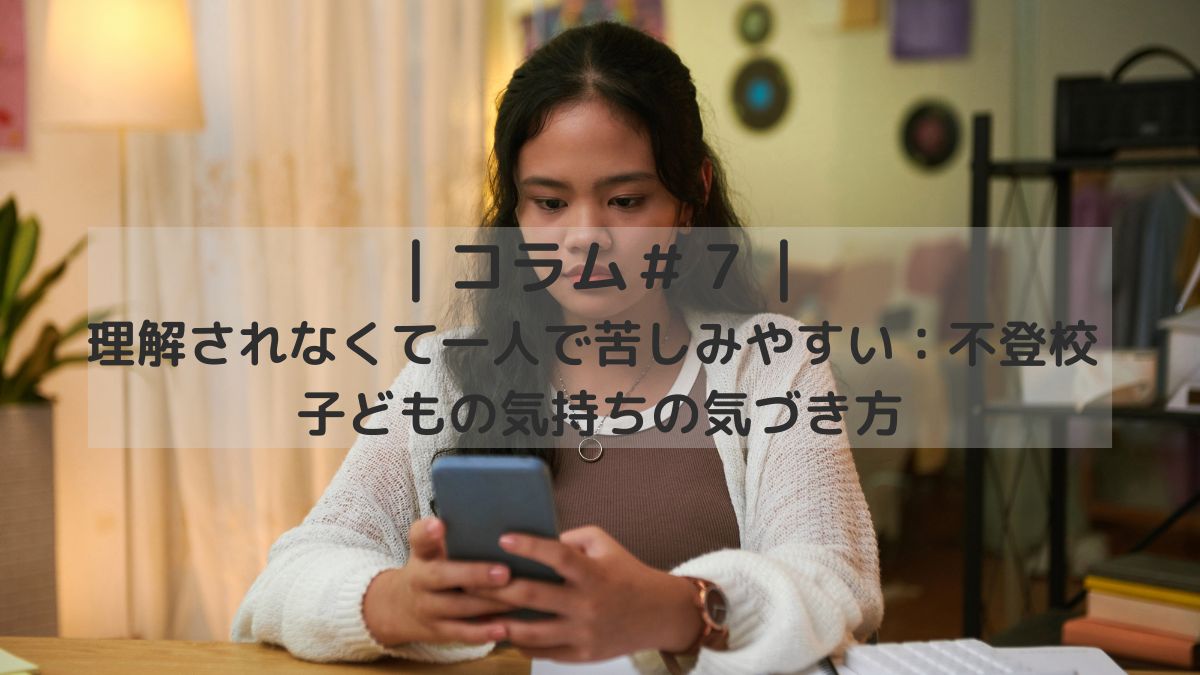はじめに
こんにちは、いまにしこころの相談室の今西です。
令和5年3月に文部科学省から、COCOLOプランという、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策が取りまとめられました。
今回、COCOLOプランを見る機会があり、不登校の最近の状況と、子どもの気持ちの気づき方についてまとめてみたいと思います。

不登校の現状
不登校は令和5年度の文部科学省の調査では、小中学生が36万6000人、高校生が6万8000人と過去最大で、年々増加傾向です。
通信制高校の利用が30万人を超えるなど、これも過去最高で、不登校の広がりが背景にあると言われているようです。

COCOLOプランとは
不登校により学びにアクセスできない子ども達をゼロにすることを目的とし、誰一人取り残されない学びの保障を社会全体で実現するためのプランとのことです。要約すると以下の通りです。
1不登校の児童生徒すべての学びの場を確保し学びたいと思った時に学べる環境を整える
主に教室以外で学校の居場所をつくる不登校特例校や、行内教育支援センターを設置すること。
学外の教育支援センターの機能強化、多彩な学びの場や居場所の確保としてフリースクールなどとの連携強化を行っていくようです。
2こころの小さなSOSを見逃さず、「チーム学校」で支援する
心身の調子を一人1台持つ、端末を活用し気づけるようにすること。校内の多彩な専門家(教師やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、養護教諭など)で協力し支援することや、保護者の相談窓口を整備していく。
3学校の風土の「見える化」を通じて、学校を「みんなが安心して学べる」場所にする
いじめなどの対応の強化や、学校の風土を「見える化」して、関係者が共通認識を持って取り組めるように整備していく。
詳しくは、文部科学省のページをご参照ください(タップするとホームページへ移動します)

不登校の要因について
様々な取り組みによって、支援の幅が広がってきていると言えますが、なかなか、不登校は難しいものです。
その理由として不登校の要因は一つの原因で起こっているものではなく、複合的な要因が重なって起きているものと考えられます。
① 心理的・情緒的な不安…自分らしさへの苦しみ、いじめ、自己肯定感の低下、思春期の感情の揺れなど
② 学業への不適応…授業についていけない、成績が思うように伸びない、進学による学習不可の増加など
③ 家庭環境の影響…家庭内の不仲、過干渉、経済的困難、安心できる居場所が言えにないなど
④ 発達特性・心の病気など…神経発達症(発達障害)やグレーゾーンの特性を持つ子どもたちは、周囲とのコミュニケーションや集団行動に困難を抱えやすいです。また時にうつ病や不安症といったこころの病気が影響している場合もあります。
不登校は、子どもが「学校に行けない・行かない」のではなく、「学校に行かないという選択をせざるを得ない状況」に追い込まれている場合もあります。
子どもの様子の変化をとらえ、子どもの声に耳を傾けていくことが大切なポイントです。

子どもの気持ちの気づき方
子どもの様子の変化をとらえるのは難しいですが、いくつかのポイントを押さえておくことで気づきやすくなるかもしれません。
子どもが「学校に行きたくない」と言葉に出さなくても、日常の中で不安や困りごとのサインを出している場合があります。
以下のサインは、不登校やひきこもりのサインとして見られることもあります。
・朝になると体調不良を訴える(腹痛・頭痛・吐き気などが繰り返し出る)
・表情が暗い・笑顔が減る(以前より元気がない、無気力そうに見える)
・イライラが増える(ちょっとしたことで怒る、家族に八つ当たりする)
・言葉数が減る(学校や友達のことを話さなくなる、会話を避ける)
・生活リズムの乱れ(夜更かし・朝起きられない・食欲の低下や過食)
・趣味や好きだったことに興味を示さなくなる
・学校の持ち物を準備しなくなる、忘れ物が増える
・「疲れた」「行きたくない」とつぶやくことが増える

これらのサインは一時的に誰にでも起こる可能性が起こるものですが、繰り返し見られる場合や、長く続く場合、学校に行く場面になるとよくみられるといった場合には注意するとよいかもしれません。
「心配だから問い詰める」のではなく、「ちょっと気になることがあるけど、大丈夫?」と安心して話せる雰囲気をつくることが大切です。
学校に行きたくないと言っても怒るのではなく、一度、「今は、学校に行きたくない気持ちなんだね」と受け止めてあげることも大切です。
サインに気づき、早い段階で子どもの気持ちを受け止めることができると、不登校やひきこもりの予防や改善につながる場合もあります。

おわりに
今回は、不登校の現状と、子どもの気持ちへの気づき方についてまとめてみました。
「学校に行きたくない」と言った際に、いきなり怒ってしまうと、それ以降、本当の気持ちを話してくれるまで、時間がかかってしまう場合があります。
あまり一般的にはいいことではない事でも、一度、「今、あなたはそういう気持ちなんだね」と受け止めてあげることで、本当の気持ちを話してくれやすくなる子どももいます。
家族としては冷静になれず、感情的になってしまいやすい部分かもしれませんが、少し心のかたすみに覚えておかれるといいかもしれません。
次回は、「親ができるかかわり方」についてまとめてみようかなと思っております。
最後までご覧いただきありがとうございます。

参考文献・ホームページ




いまにしこころの相談室
代表 今西 広嗣